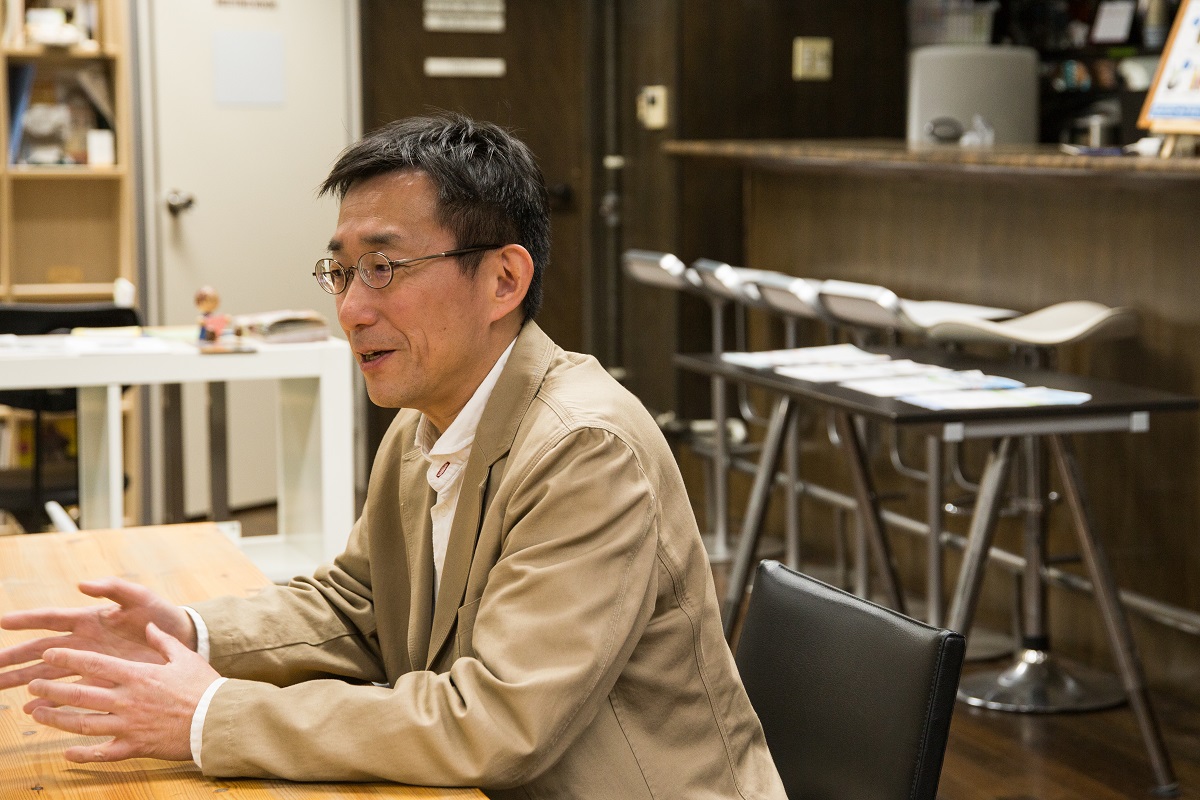だれをも受け入れる緩やかな場所、完成図のない未来を、地域とともにつくり続けたい。
キャリアの始まりは、ケーブルテレビの制作から。ずっと「専門的な仕事に憧れていた」という中村さん。目の前の仕事をこなす日々の中で、ある日、「一生の仕事」と思えることに出会ったといいます。中村さん自身が、これまでどんなキャリアを歩み、道を選んできているのか。「まちのキャリアラボ」リーダーも務める中村さんのマイストーリーを紐解きます。
―それでは「キャリアヒストリー」お聞きします。緊張しますね(笑)まずは、茅ヶ崎との関わりから、お話しいただけますでしょうか。
中村 職場が茅ヶ崎なんです。メジャーな地名なので前から知っていましたし、湘南の、カッコイイ地名、というイメージです。
―容さんは、はじめから「キャリア」や「教育」に興味があったんですか?
中村 いえ、そんなことはありません。社会人のスタートは、ケーブルテレビでした。地域情報番組の制作をしていたんです。その仕事、すごくハードで……。20代後半のとき過労で入院したこともありました。
―そこから、どうしてキャリアに興味を?
中村 37歳くらいのときに、大学で就職支援に関わったことがきっかけです。
でもそれも、最初から就職支援の仕事に就いていたわけではありません。学生時代お世話になった方から、「大学職員に欠員が出たから誰かいないかな?」と言われて。条件も悪くなさそうだったし、前言ったみたいにテレビの仕事はハードで30代・40代で続けてく自分が想像できていなかったから、僕で良ければやらせてください、って軽いノリで、大学職員になりました。
―最初から教育の軸で働き始めたわけではなかったんですね。
中村 はい。でも、実はずっと「何かの専門家になりたい」って、専門性に憧れをもっていたんです。テレビの仕事をやっているうちに、そのことを忘れてしまってたんですよね。それで、環境に惹かれて飛び込んでみた大学事務だけど、そこに専門性が見出せなくて、転職当初はとっても後悔した。
―後悔してたんですか!そのときは、辞めよう、とは思わなかったんですか?
中村 うーん……環境面での魅力が大きくて。
今でもハッキリと覚えているんだけど、番組制作の仕事で地域で活動している人を取材に行ったことがあったんです。準備しているときは、「なんか冴えないおじさんだなあ」って思っていたんだけど(笑)いざ始まって、ファインダー越しに見たその人が、とても輝いて見えた。そのとき、自分の青さに衝撃を受けましたね。自分は、この仕事を外したら何が残るんだろうって思って。その時、取材される側の方が素敵だなって思ったんですよね。
それで、別の場所で何かを得るとしたら、大学事務って時間があってよいのかなって。
―なるほど。じゃあ、教育に興味を持ち始めたのはいつからですか?
中村 10年くらい経ったとき、学生の就職支援をする部署に移ったんです。そこで、専門性の必要性を感じました。それから、学生の進路を決めることに関わる仕事が自分に合いそうな直感があったんです。
―直感て、どんなですか?
中村 初めて部署に行ったとき、ベテランと言われている方と一緒に学生の面談に入ったことがあったんです。そのとき、本当にひどかった。
―ひどい、ですか??
中村 そう、びっくりするくらい。面談するうちにどんどん学生が下を向いていく様子なのに、そのベテランの人は、「良いこと言ってやった」みたいな感じで。その時、自分の価値観や経験則だけでやっていたらダメな仕事だ、専門的なことを勉強しなくちゃ、と思ったんです。そうしているうちに、この仕事を「一生の仕事」にしても後悔しないだろうな、と。
ー学内で、キャリアを支援することの面白さを体験して、そこから外へ目を向けたきっかけは、何がありましたか?
中村 学校でできることの幅に限界を感じたことですかね。学校の枠にはまらない学生って多いんです。それを無理にはめようとすることで、余計な悩みを生んでしまうことがある、と感じていました。そこにはめることなく、何かためになる場所が必要だって、だんだんと感じ始めていきました。
―なるほど。
中村 10年間、キャリア支援をしていたのですが、5年目からそういうことを感じていましたね。「なんともならないな」とモヤモヤしているタイミングで、違う部署に異動になりました。職場の都合で、自分が「一生の仕事かも」と感じていたものから切り離されて、その時、自分が「職場に依存していた」と気づいたんです。
―依存、ですか。
中村 やりたいと思っていたことって、実は自分の中から出てくる動機ではなくて、人にゆだねていたんだって。じゃあ、組織に不満を言っている自分が間違っているんじゃないか?と感じ始めて、だったら外でやるしかないのかな、とぼんやりとですが感じ始めました。
でも、職場を辞めると考えたとき、民間の人材ビジネスくらいしか選択肢が浮かんでこなくて。当時40代後半だったから、自分の基盤や健康面のリスクを考えたとき、とはいえ今の状況を受け入れるしかないのかな…と思ったり……モヤモヤした状態がしばらく続いていました。
―チガラボとの出会いは、いつですか?
中村 5年くらい、モヤモヤした状態が続いた後、茅ヶ崎のキャンパスに異動になりました。キャリアに関わる仕事には戻ることはできなかったんですが、そのタイミングでチガラボに出会いました。
―チガラボの印象はどうでしたか?
中村 「はまらない人たちの働き方・生き方を手伝える仕組みをつくりたい」って、チガラボ代表の清水さんに行ったら、「やってみたら?」って言われて。(笑)そのあと、「具体的にどんなことできます?」「いつやります?」ってトントン拍子に決まっていって、気付いたら、CareerBARをやっていた。(笑)
チガラボのオープンのタイミングで、「ラボ(実験室)だから、なんでもありです」って軽いノリで。いままでの自分は、準備に準備を重ねる慎重な環境で過ごしていたから、その気軽さ・気楽さが衝撃的でしたね。新しいタイプの人たちに出会った感じでした。
―初回、CareerBARをやってみてどうでしたか?
中村 自分がイメージしたことを形にしていくのはとても楽しかった。今思い返すと整えなければならなかったことはあったけど、やってみてから整える、というのもありなんだなって、その時気づきました。
まず、やってみる。それによってどんどん整えられていくプロセスを味わうことができたのはよかったし、自分にもできたんだから、ほかの人だってできる。それに気付くことで、ほっと肩の力を抜ける人が増えればと思いました。
―「まちのキャリアラボ」について、これからの展望を聞かせてください。
中村 まちのキャリアラボは、メンバーが固定されず、自分がやりたいことをやりながら、チームで形にしていく。そんな場所です。関心を持った人たちが、関心を持ったタイミングで集まってつくる。
サグラダファミリアってあるでしょう。あんなふうに、いつまでも完成することなく、つくられていくような。形はきまっていなくて、想いを共通する人たちが入れ替わり入って形を作っていく、そういうチームになれたらいいなと思っています。一旦外へ出て、戻ってくるのももちろんアリです。
―活動の在り方としては、いかがですか?
中村 チームとしてスタートすると、どうしても「役割」が生まれてきてしまうけれど、僕は、「やらされ感」がないようにしたいと思っています。かくいう僕自身も、本業やりながら大変だな、とか感じることがあるけれど、「リーダーだから」とか「関わっちゃったからにはやらなきゃ」って責任や拘束を感じることなく、あくまでも緩やかさを大切にしたい。緩やかに、でも確実に。実現していきたいですね。
―容さん自身のキャリアはどうですか?
中村 本業の大学はまだ続けていて、並行してこうした活動を続けているわけだけれど、まちのキャリアラボが、自分の人生の柱になったらいいなと思っています。誰かのやりたいことをサポートする、それが本業になればと。
―茅ヶ崎という地域に対しては、どうでしょうか。
中村 これまでの世の中は、企業・組織の中でどう力を発揮できるか、が重要でした。でも、今の時代は、一人ひとりが自分の生活圏内でどれだけ生き生きと過ごすことができるのか。それによって豊かさを感じられるのではないかな。
仕事は仕事であるけれど、地域だったらもっと自分が満たされることができそうじゃないか、って、活動を始める人が増えれば、どんどん生き生きした人が増える。茅ヶ崎の街がそれを受け入れる緩やかさを持って、そしたら、そういう緩やかさを求める人たちが集まって……窮屈さを感じたり、我慢したりして人生の時間を使う人が少なくなる。子どもたちがそういう大人を見て育てば、より豊かな人生の選択肢を広げていけるのではないかなとも思うんです。そのためにできることを、この茅ヶ崎で見つけていきたいと思っています。
―ありがとうございました。
<インタビューを終えて>
これまでのキャリアの中で感じられてきたこと、迷いを含めて率直にお話いただき、今でこそ、キャリアや教育といったブレない軸を持っているように感じる容さんが、こうした経験を経て、今の考えや姿にたどりついているんだなあと、まさにヒストリーを感じました。容さんが歩んできたこのストーリーは、きっと誰にでも、「私と/僕と同じだな」と思える部分があるのではないでしょうか。(かくいう私も……)
「緩やかに、でも、確実に」肩の力を抜いて楽しみながら興味のあることに触れていることが、人生をちょっと満たす、そんな一歩になるのかなと思いました。
インタビュー:木村 宏美
写真:岩井田 優
編集:もりおか ゆか